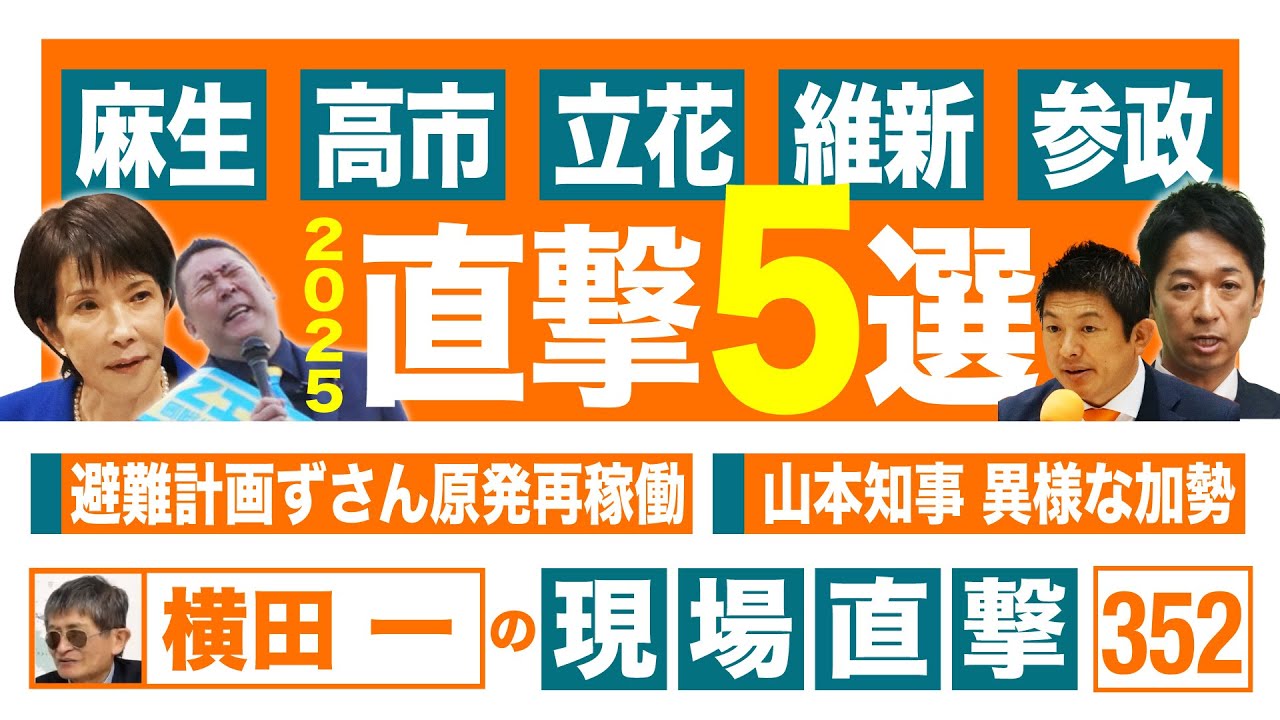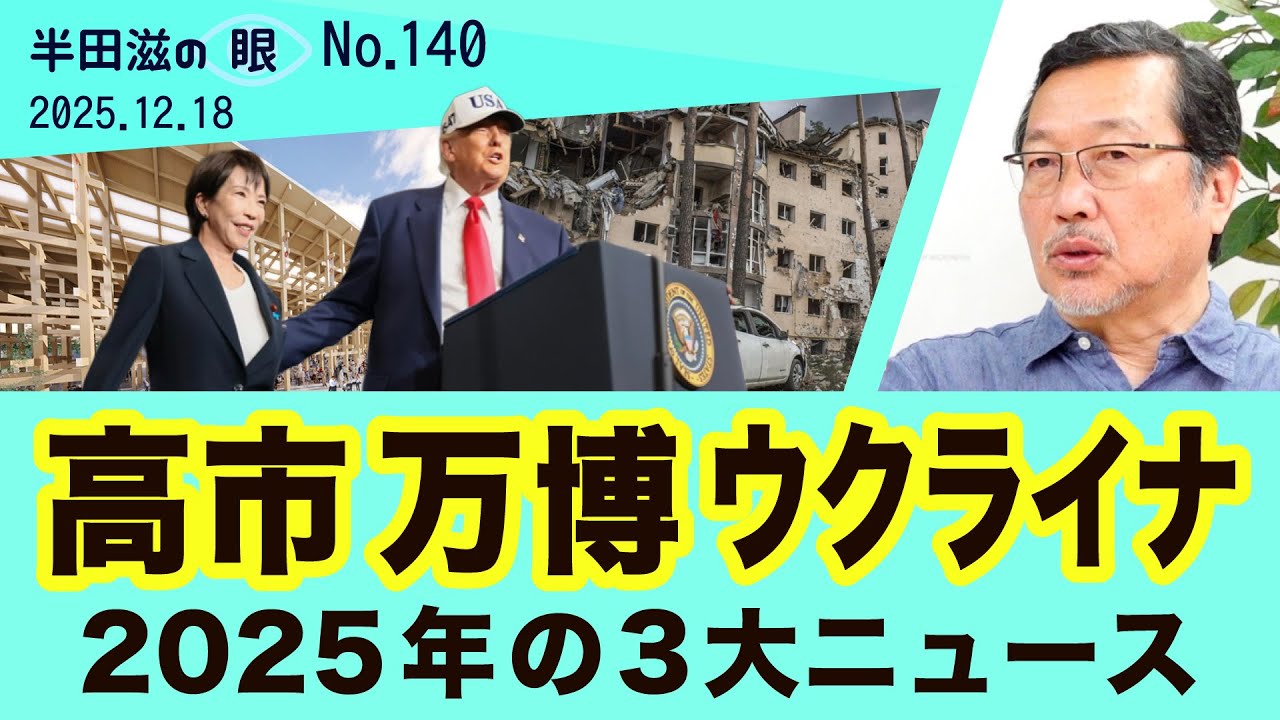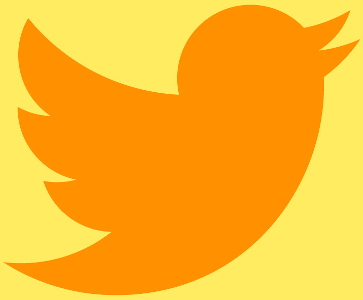能登半島地震の発生後、石川県庁は初動対応に失敗した、といわれる。
動画一覧
2026年、あけましておめでとうございます。
2024年1月1日 16時10分、石川県能登地方で大規模な地震と津波が発生し、多くの方が被害を受けました。
2026年が明けました。デモクラシータイムス最初の番組は恒例の「元日スペシャル」。弊チャンネルでおなじみの論客4人の方にお集まりいただき、「政治」「外交・国際政治」「経済・生活」「安全保障・防衛」の4テーマで、26年を展望します。今年もデモクラシータイムスをご支援よろしくお願いいたします。
被災地 能登から高市政権への提言「心が疲れたら、いのちの声を聞け」
紅白を見ない皆様にお届けする、激動と混沌の2025年の締めくくり、爆走する3ジジの語り納め。
北丸雄二と辛淑玉が、マスメディアでは見落とされがちな社会の課題を拾い上げ、マイノリティからのまなざしで語り合い、本質を見抜き、怒り、笑い、ため息をつきながらも前に進む縦横無尽の1時間番組(ときどき長くなる)。
今週も採れたて横田さんの現場レポート!
防衛ジャーナリスト半田滋が取り上げる2025年の3大ニュース